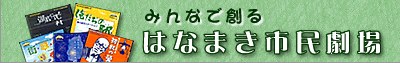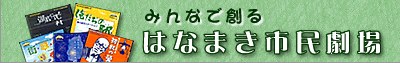|
《―公演写真を掲載しました―》
第42回花巻市民劇場公演「多田等観物語 日が昇る 観音山に帰りたい」が無事公演の公演写真が出来上がりましたので掲載しましたのでどうぞご覧ください。また、大きいサイズの写真はこちら「第42回公演拡大写真」からごらんください。
《H30.3.29》
◆◇◆Photo◆◇◆
 |
 |
1.熱演のひとこま |
2.熱演のひとこま |
 |
 |
3.熱演のひとこま |
4.熱演のひとこま |
 |
 |
5.熱演のひとこま |
6.熱演のひとこま |
 |
 |
7.熱演のひとこま |
8.熱演のひとこま |
 |
 |
9.熱演のひとこま |
10.熱演のひとこま |
 |
 |
11.熱演のひとこま |
12.熱演のひとこま |
 |
 |
13.熱演のひとこま |
14.熱演のひとこま |
 |
 |
15.熱演のひとこま |
16.熱演のひとこま |
 |
 |
17.熱演のひとこま |
18.熱演のひとこま |
 |
 |
19.熱演のひとこま |
20.熱演のひとこま |
 |
 |
21.熱演のひとこま |
22.熱演のひとこま |
 |
 |
23.熱演のひとこま |
24.熱演のひとこま |
 |
 |
25.感謝のお見送り |
26.感謝のお見送り |
《―公演終了。皆様ありがとうございました。―》
花巻市民劇場実行委員会会長 高橋信也
おかげさまで、第42回花巻市民劇場公演「多田等観物語 日が昇る 観音山に帰りたい」が無事公演を終えることができました。
これもひとえに、多くの皆様のご理解、ご支援によるものと会員一同心よりお礼申し上げます。
ご承知のとおり、私たち市民劇場実行委員会は、花巻の地域文化の「原点」として、花巻の文化と歴史に題材を求め、市民の手づくりによる舞台を作り上げて、まちづくりの一つとして創作活動を展開して参りました。今回の公演作品は、昨年、没後五十年を迎えられた、「多田等観」を題材として、二十八回で公演したものを脚色して再度取り組むことに致しました。
「多田等観」とは誰?とか、何をした人なのか、花巻との関係は?と言うことを中心にした内容でした。
過去に現存した偉大な人物を認識し、ともに世代を超えて偉大な人物を心の財産として、誇りに思える舞台づくりができ、お客様に感動していただければ、これに勝る喜びはございません。
終わりにあたり、私たち「手づくりによる舞台」のために、お忙しい中をご来場いただきました皆様に心から感謝をいたすとともに、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
「公演の記録」ページを更新しました。
《H30.2.27》
《第42回花巻市民劇場練習風景》
本番を目前に控え、練習も最終段階へ。その練習のひとこまを紹介します。ご期待ください。

【公演名】「多田等観物語 日が昇る 観音山に帰りたい」
【脚本】 鹿川比呂史
【演出・脚色】高橋信也
【公演日時】
・1日目 平成30年2月24日(土)午後6時30分開演
・2日目 平成30年2月25日(日)午後2時開演
【入場料金】 一般:1,000円 高校生:500円 中学生以下:無料
《H30.2.23》
《第42回花巻市民劇場「多田等観のあゆみ」》

第42回花巻市民劇場公演のチラシが完成し手に入るようになりました。今回はチラシ裏面で紹介されている「多田等観のあゆみ」をご紹介いたします。多田等観を理解する参考になれば幸いです。公演まで約1か月半。どうぞ楽しみにお待ちください。
多田等観のあゆみ
明治23年、秋田市土崎港の西舟寺14世義観の3男として生まれる。明治43年、秋田中学校を卒業後、西本願寺に入山、修行中チベット王のダライ・ラマ13世の特使の世話役になり、チベット語を会得した。特使の帰国に際し、西本願寺法主の命によりインドに同行、同地に逗留中のチベット王から入国を許可された。大正2年、ヒマラヤ山脈を越えて単身でチベットに入国、王の特命により学僧としてセラ学問寺に入学。国王の庇護のもと10年間、あらゆる修業を積むと共に、チベット仏教の研究、仏典、文献の収集に努め、大正11年、ラマ教の最高学位であるゲシェー(大僧正)に任じられた。その後、病気治療のため帰国、東京大学、東北大学等の講師を歴任。太平洋戦争の激化に伴い、チベット請来の文化財を守るため、実弟である花巻市南河原の光徳寺住職鎌倉義蔵のもとに疎開。その後円万寺観音堂境内に村人から「一燈庵」の寄贈をうけ、さらに経蔵の建立を得て経典、書籍等を収蔵。昭和26年に渡米のため花巻を去るが、経典、仏具等は光徳寺の「蔵脩館」に納められた。昭和30年に「日本学士院賞」受賞。昭和41年秋の叙勲で「勲三等旭日中授章」を受賞。昭和42年に76歳で没した。
------------------------- 講演の概要 -------------------------
【公演名】 第42回花巻市民劇場
「多田等観物語 日が昇る 観音山に帰りたい」
【脚本】 鹿川比呂史
【演出・脚色】高橋信也
【公演日時】
・1日目 平成30年2月24日(土)午後6時30分開演
・2日目 平成30年2月25日(日)午後2時開演
【入場料金】 一般:1,000円 高校生:500円 中学生以下:無料
《H30.1.14》
《第42回花巻市民劇場旗揚げ》
 平成29年11月20日(月)花巻市文化会館第1・2会議室において、午後6時30分から来賓も含めおよそ30名が集まって、「第42回花巻市民劇場旗揚げ」が開催されました。 平成29年11月20日(月)花巻市文化会館第1・2会議室において、午後6時30分から来賓も含めおよそ30名が集まって、「第42回花巻市民劇場旗揚げ」が開催されました。
旗揚げでは、公演の概要が説明され公演の成功に向けて本格的に動き始めました。
講演の概要は次のとおりです。
【公演名】 第42回花巻市民劇場
「多田等観物語 日が昇る 観音山に帰りたい」
【脚本】 鹿川比呂史
【演出・脚色】高橋信也
【公演日時】
・1日目 平成30年2月24日(土)午後6時30分開演
・2日目 平成30年2月25日(日)午後2時開演
【入場料金】 一般:1,000円 高校生:500円 中学生以下:無料
《H29.12.7》
《第42回花巻市民劇場公演情報》
○名称:第42回花巻市民劇場公演
『多田等観物語 日が昇る 観音山に帰りたい』
○日時:平成30年2月
・24日(土) 午後6時30分開演(午後6時開場)
・25日(日) 午後2時開演(午後1時30分開場)
○場所:花巻市文化会館 大ホール
○料金:一般1,000円 高校生500円 中学生以下無料
○チケット発売日:近日発売予定
※前売と当日の料金は同一です。
※24日と25日の共通券です。
※全席自由です。
【問い合わせ】 花巻文化会館 TEL 24−6511
《H29.11.20》
《文化会館バックステージツアー&演劇ワークショップ実施》
文化会館バックステージツアー&演劇ワークショップが8月3日(木)に市民20名が参加して行われました。バックステージツアーでは舞台、照明、音響装置を実際に操作して体験しました。ワークショップではわらび座の俳優椿千代さんと尾樽部和大さんを講師に迎えて発声練習や体の使い方を学び、寸劇の稽古も行いました。
◆◇◆Photo◆◇◆
 |
 |
バックステージツアーのひとこま |
バックステージツアーのひとこま |
 |
 |
演劇ワークショップのひとこま |
演劇ワークショップのひとこま |
 |
 |
演劇ワークショップのひとこま |
演劇ワークショップのひとこま |
《H29.8.6》
《文化会館バックステージツアー&演劇ワークショップ》
普段見ることができない舞台裏を、見て、体験することができます。ステージから見渡す景色を体験してみよう!ワークショップでは楽しく体を動かしてみましょう。演劇の「はじめの一歩」を踏み出してみませんか?
・名称:文化会館バックステージツアー&演劇ワークショップ
・日時:平成29年8月3日(木)
(1)バックステージツアー 10時〜11時30分
(2) 演劇ワークショップ 13時〜16時
・場所:花巻市文化会館
・参加費:200円((1)(2)両方参加でも同料金)
・申し込み方法:住所、氏名、年齢、電話番号を来館、電話、ファックスにより文化会館までお申し込みください。
・申し込み締め切り:7月30日(日)
・その他:
※動きやすい服装でご参加ください。
※小学生は保護者同伴でご参加ください。
※バックステージツアーとワークショップの両方に参加の方は、昼食をご持参ください。
◎問い合わせ・申し込み:花巻市民劇場実行委員会事務局(花巻市文化会館) 電話:0198-24-6511 FAX:0198-22-4321
《H29.7.7》
《花巻市民劇場の脚本を募集》
花巻市の偉人・文化や歴史などを題材とした、多くの方が参加できる2時間以内の作品を募集します。採用された作品は、平成30年度の市民劇場で上演します。
第43回目となる公演に、脚本づくりへペンを走らせてみませんか?
・応募期限:平成29年10月30日(月)
・応募方法:縦書き右とじの用紙に書いた作品に、
(1)住所
(2)氏名
(3)年齢
(4)職業
(5)電話番号
を記入し、持参または郵送で文化会館(〒025-0097 花巻市若葉町3-16-22)へ。
※作品は未発表のものに限ります。また、応募作品は返却しません。
【問い合わせ】 花巻文化会館 TEL 24−6511
《H29.4.18》
《平成29年度花巻市民劇場実行委員会総会》
平成29年度の花巻市民劇場実行委員会総会が、平成29年4月12日(水)午後7時から、花巻市文化会館第5・第6会議室で開催されました。
《H29.4.13》
《・・・公演の記録ページ更新・・・》
これまでの花巻市民劇場公演については、公演の記録ページをごらんください。
◇平成29年の新着情報は「新着情報 H29」をご覧ください。
|